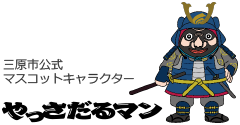本文
自主防災組織 避難訓練手順書を作成しました!
自主防災組織 避難訓練手順書を作成しました!
避難訓練を企画するときに活用してください!
自主防災組織が避難訓練を行う際の手順と必要な様式を、組織の皆さんに参考にしていただくために作成しました。
近年の異常気象や南海トラフ巨大地震の発生のおそれなど、地域での避難訓練の重要性が高まっている中、地域で避難訓練を実施していただくことで自主防災組織の活動の活性化と、地域の防災力の向上を目的としています。
「避難訓練をしてみたいけど、どうやればいいかわからない」「いつも同じ訓練をしているけど、違うこともやってみたい」と思われている役員さんや地域防災リーダーさんは、ぜひ活用してください。
避難訓練手順書 [PDFファイル/733KB]
様式集 [ZIPファイル/1.59MB] 様式集 [PDFファイル/940KB]
地域の実情に合わせて修正してください!
手順書でお示ししているスケジュールや訓練の内容等は、あくまでも参考例です。訓練内容や様式の変更、スケジュールの省略等、地域の実情に合わせて行ってください。
避難訓練の手順(例)
避難訓練手順書でお示ししている手順は、次の7手順です。
1 訓練までの年間スケジュールを立てましょう(4~5月)
年度当初に年間スケジュールを立てましょう。予算が伴う場合は、総会で承認を得る必要がある場合もありますので、町内会や自主防災組織の規則に基づいて準備しましょう。
使用する様式(例) 別紙1 [Wordファイル/11KB]
2 訓練の概要を決めましょう(訓練の4か月前)
いつ、どこで、誰が、どんな訓練を、どの災害を想定して、何を目的に行うかを決めましょう。地域の行事に合わせて実施すると、地域の皆さんも集まりやすくなります。
※地域の行事:運動会、夏祭り、盆踊り、秋祭り、町内一斉清掃作業、クリスマス会、とんどなど
使用する様式(例) 別紙2 [Wordファイル/10KB]
3 訓練当日のスケジュール、役割、準備物を決めましょう(訓練の3か月前)
訓練当日の大まかな内容とスケジュール、役割分担、必要な準備物を決めましょう。
使用する様式(例) 別紙3 [Wordファイル/15KB]
4 訓練の詳細、シナリオを決めましょう(訓練の2か月前)
訓練の詳細を決めましょう。シナリオもあると役員間でのイメージが共有しやすくなり、また、役員が交代しても次年度以降の訓練の準備がスムーズになります。
使用する様式(例) 別紙4 [Wordファイル/16KB]
5 町内に周知しましょう・補助金を申請しましょう(訓練の1か月前)
地域の皆さんに詳細をお知らせするため、町内回覧等で周知しましょう。
使用する様式(例) 別紙「町内回覧」 [Wordファイル/823KB]
訓練の補助金を活用する場合は、事前に申請をお願いします。
補助金については自主防災組織の活動を支援しています(補助金など)のページ「2 育成支援事業補助金(組織の活動に対する助成)」をご覧ください。様式や記入例も掲載しています。
6 訓練をしたら振り返りましょう(訓練当日)
使用する様式(例) 役員での振り返り→別紙5 [Wordファイル/11KB]
参加者へのアンケート→別紙「参加者アンケート」 [Wordファイル/14KB]
7 町内に訓練の報告をしましょう・補助金の実績報告をしましょう(訓練後)
訓練の結果を地域の皆さんにお知らせしましょう。
使用する様式(例) 別紙6 [Wordファイル/721KB]
補助金を活用した場合は、実績報告もお願いします。実績報告についても自主防災組織の活動を支援しています(補助金など)のページ「2 育成支援事業補助金(組織の活動に対する助成)」をご覧ください。
津波避難モデル訓練
南海トラフ巨大地震を想定した津波避難のモデル訓練を紹介しています。津波浸水想定区域内の地域の訓練の参考にしてください。
別紙「津波避難モデル訓練」 [Wordファイル/13KB]
津波避難モデル訓練シナリオ [Wordファイル/18KB]
チラシ(地震の備え) [PDFファイル/1.11MB] チラシ(感震ブレーカー) [PDFファイル/857KB]
市内自主防災組織の活動事例
市内の自主防災組織が行っている活動を紹介しています。組織の活動の参考にしてください。
詳しくはこちらからご覧ください。→自主防災組織の活動を紹介します!
避難訓練と一緒にやってみましょう
避難訓練と一緒に行うことで、地域の防災力をより高めることができる訓練等を紹介します。詳細については危機管理課へ相談してください。
・段ボールベッド組立訓練 ・炊き出し訓練 ・AED救命講習 ・消火器訓練
・個人の避難行動計画(マイ・タイムライン)作成研修
・住民参加型の訓練(避難所運営ゲーム(HUG)、クロスロードゲーム、なまずの学校、防災ぬりえ、
地図を使った災害イメージ訓練(DIG))
連携機関を紹介します
訓練を実施するに当たり、協力可能な機関を紹介します。
市(危機管理課)
・備蓄食料、水の提供
賞味期限間近のものを提供します。自主防災組織に対して年1回照会します。受渡時期や必要数等ご希望に添えないことがありますので、あらかじめご了承ください。受渡時期は秋以降となります。
・段ボールベッド、簡易トイレの貸出
市が備蓄している段ボールベッドや簡易トイレを貸し出します。組立訓練に活用してください。
・防災資機材の貸出
発電機や防災かまど等を貸し出します。訓練で活用してください。燃料代はご負担いただくことになります。
消防署(三原消防署・三原西消防署)
・消火器訓練
水消火器を使用した初期消火訓練です。
・AED救命講習
訓練用AED(自動体外式除細動器)を使用した救命講習です。
三原市防災ネットワーク
市内13の防災関連団体で構成し、市民生活の「安心・安全」確保に向け、地域の防災力向上を図っている団体です。日頃から構成団体間で情報交換及び緊密な連携を進め、平時には防災啓発活動等の開催を、災害時には各専門知識を活かした支援活動を実施しています。
各団体の専門分野を活かしたサポートが可能ですので、連携したい場合は、危機管理課までご連絡ください。
三原市防災ネットワークについてはこちらで詳しく紹介しています。→三原市防災士ネットワークの活動・構成団体を紹介します!