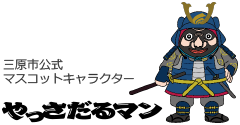本文
三原市消防団とは?
自分たちの町は自分たちで守ろう!!
消防団とは・・・
「自分たちの地域は自分たちで守る」という精神のもと、火災や災害が発生したときに自宅や職場から現場へ駆け付け、その地域での経験を生かした消火・救助活動を行うものです。また、消防団は消防本部や消防署と同様に市町村に設置される公的な機関であり、団員は特別職の地方公務員です。
消防署と消防団の違い
消防署職員は、災害対応が仕事です。このため、常時勤務し、災害対応や訓練を行っています。消防団員は、農業、自営業、会社員など、自分の仕事があります。このため、地域での火災及び災害発生時、訓練時、災害警戒時など、必要に応じて出動します。
三原市消防団のあゆみ
永禄10年(1567年)小早川隆景によって三原城が築城され、城下町としての歩みを始め我が町「みはら」。
江戸時代には大名消火と町消火とがあり、我々消防団は町消火の流れを汲んだ組織です。
昭和14年警防団として発足し、昭和22年10月消防団として再編成されました。
平成17年3月22日本郷町、久井町、大和町と旧三原市の1市3町が合併し、現在の三原市となりました。
市町村合併に伴う消防団の統合や、その後の条例改正を経て、1本部7方面隊31分団体制(定数1,250名)となりました。
令和6年4月1日現在で団員数は、1,164人です。(基本団員1,098人・機能別団員66人)
消防団員の処遇
消防団員は災害現場で活動するため怪我をしてしまうかもしれません。
そんな時のためにつぎのような制度があります。
○公務災害補償制度(主なもの)
1.療養補償 … 消防団活動中に怪我などをした場合の治療費
2.休業補償 … 消防団活動中の怪我などで収入を得られない場合
3.傷病補償年金 … 消防団活動中の怪我などが長期間治らない場合
4.障害補償 … 消防団活動中の怪我などが原因で障害が残った場合
5.遺族補償 … 消防団活動中の怪我などが原因で死亡した場合
※公務災害補償はいずれも消防団活動中の怪我などが原因のものに限られます。
消防団員(基本団員)は、消防協会(団員同士の助け合いのため組織)の会員です。
このため、以下のような福利厚生制度があります。
○福利厚生制度
1.福祉共済制度 … 団員の死亡・7日間以上の入院などで共済金を支給
2.B型火災共済制度 … 家屋が火災・風水雪害に被災した場合に共済金を支給