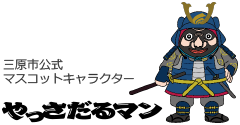本文
応急手当の基礎知識
応急手当とは
私たちの周りで突然発生するケガや病気に対して、救急隊に引き継いだり、病院へ行くまでに行う手当のことをいいます。
ケガや病気の中で最も重要なことは、心臓や呼吸が止まってしまった場合です。
その原因は,急性心筋梗塞や脳卒中であり、その他にプールで溺れる、のどに餅を詰まらせる、ケガで大出血するといったことも原因として挙げられます。
そのような時、近くに居た人ができる応急処置を「救命処置」といいます。
救命処置の重要性
救命処置を行い、社会復帰に導くための一連の行動を「救命の連鎖」といいます。
ケガや病気が発生した場合、早期認識と通報、そして一次救命処置(心肺蘇生とAED)が行われた方が、生存率や社会復帰率が高いことが分かっています。
また、「心停止の予防」として急性心筋梗塞や脳卒中にみられる初期症状に気づき、少しでも早く救急車を呼んで、病院で治療を受けることも救命の連鎖の一端となります。

人は心臓や呼吸が止まると、その後約10分の間に救命率が下がります。このような場合、一刻も早く「119番通報」をして救急隊を要請し、救命処置を受けながら病院へ搬送することが重要となります。このように、各々が役割を果たして救命のバトンを住民から救急隊へ、救急隊から医師へと繋げて行くことを、「救命のリレー」といいます。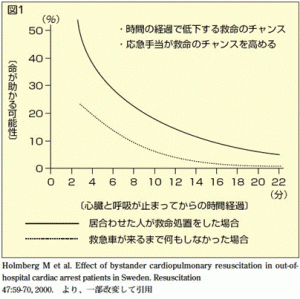
また、早期の「119番通報」は救急隊の到着までに全国平均8.5分間かかる空白の時間に、指令センターの指示を受け、応急手当ができるだけでなく、不安な気持ちを和らげるという効果をもたらすこともあります。
突然発生するケガや病気に対応するためには、知識だけではなく、「助ける」という意識も大切で、そのためには定期的に救命講習を受講することで、知識・意識を培うことができます。
いざというとき、その救命手当を行う人こそ、その場に居合わせた「あなた」なのです。

各種応急手当申し込みはこちら
心肺蘇生法リーフレット
異物除去法リーフレット