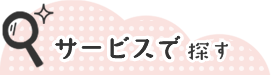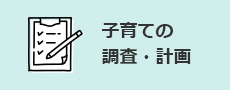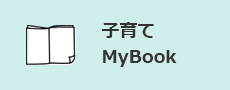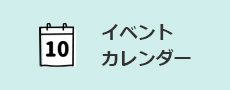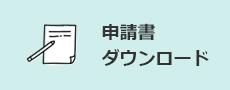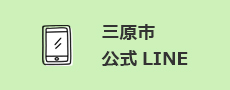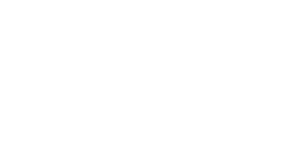本文
予防接種のお知らせ
子どもの定期予防接種のお知らせ
赤ちゃんがお母さんからもらった免疫力は、発育と共に自然に失われていきます。予防接種は病気や感染症に関する免疫をつくる助けとなります。
予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種時期などが定められた定期予防接種があります。費用は無料で、万が一重大な健康被害があった場合は健康被害救済制度があります。
| 概略 | 予防接種の前に | 予防接種の後に | 副反応 |
| 健康被害 | 実施医療機関 | 医療機関へお知らせ | 接種券の発行 |
| 県外での接種 | 予防接種のデジタル化 |
概略
対象ワクチンの種類、接種時期等は次の表のとおりです。
| 期間 | 通年 | |||||
| 対象 | 種類 | 対象年齢 | 標準接種時期 | 回数 | ||
| B型肝炎 | 生後12か月未満 |
生後2か月~8か月未満 |
3回 | |||
| BCG | 生後12か月未満 | 生後5か月~8か月に達するまで | 1回 | |||
| ヒブ(Hib) ※標準接種以外はこちらから |
生後2か月~ 60か月(5歳)未満 |
初回 | 生後2か月~7か月に至るまでに開始 生後12か月に至るまでに、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおく |
3回 | ||
| 追加 | 初回終了後 7か月から13か月の間隔をおく |
1回 | ||||
| 小児用肺炎球菌 | 生後2か月~ 60か月(5歳)未満 |
初回 | 生後24か月に至るまでに、27日以上の間隔をおいて3回接種。ただし、生後12か月を超えて 2回目を接種した場合は3回目を接種しない。 |
3回 | ||
| 追加 | 初回終了後60日以上の間隔をおいた後で、生後12か月に至った日以降に接種 | 1回 | ||||
| ジフテリア 破傷風 百日咳 ポリオ ※四種混合 |
1期 | 生後2か月~ 90か月(7歳半)未満 |
初回 | 生後2か月~12か月に達するまで 20日以上の間隔をおいて3回 |
3回 | |
| 追加 | 初回終了後、12か月~18か月までの間隔をおく | 1回 | ||||
|
ジフテリア |
1期 | 生後2か月~ 90か月(7歳半)未満 |
初回 | 生後2か月~7か月に達するまで 20日から56日までの間隔をおいて3回 |
3回 | |
| 追加 | 初回終了後、6か月~18か月までの間隔をおく | 1回 | ||||
| ジフテリア 破傷風 (二種混合DT) |
2期 | 11歳・12歳 | 11歳 | 1回 | ||
| 麻しん 風しん (MR混合) |
1期 | 生後12か月(1歳)~ 24か月(2歳)未満 |
麻しんまたは風しんにかかった場合も、 麻しん・風しん混合ワクチンを接種することができます。 かかっていない一方のワクチンでも接種できます。事前にこども安心課へご連絡ください。 |
1回 | ||
| 2期 | 小学校就学前1年間 (年長児) |
1回 | ||||
| 水痘 (水ぼうそう) |
生後12か月(1歳)~ 36か月(3歳)未満 |
生後12か月~15か月に達するまで 1回目の接種後、6か月~12か月の間隔をおく 3か月以上の間隔をおいて2回 |
2回 | |||
| 日本脳炎※特例のお知らせ | 1期 | 生後6ヶ月~ 90か月(7歳半)未満 |
初回 | 3歳 6日以上の間隔をおいて2回 |
2回 | |
| 追加 | 4歳 初回終了後、6か月以上の間隔をおく |
1回 | ||||
| 2期 | 9歳~12歳 | 9歳 | 1回 | |||
| 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 |
中学校1年生に相当する年齢 【サーバリックス】 【ガーダシル】 【シルガード】 【シルガード※15歳未満で1回目を接種する場合】 |
3回 ・子宮頸がんリーフレット(概要版) [PDFファイル/3.36MB] |
||||
| 費用 | 無料 (発熱などで保険診療を行った場合は自己負担となります。) |
|||||
| 場所 | 三原市予防接種実施医療機関 [PDFファイル/100KB] | |||||
| 申込 | 直接医療機関に申し込み。予約が必要な場合があります。 | |||||
| 同伴 | 予防接種の際は保護者が同伴してください。(やむを得ない理由で保護者以外の人が同伴する場合はこちらをクリックしてください。) | |||||
| 以下の場合は、同伴の必要はありません。 (1)日本脳炎及び子宮頸がん予防ワクチンの対象者(いずれも13歳以上16歳未満に限ります)で、保護者の同意書 をお持ちの方 (2)16歳以上の方 |
||||||
| 注意事項 | 期間や接種回数を間違えた場合、また実施医療機関以外で接種した場合は事業の対象となりません。 | |||||
| 二種混合2期(ジフテリア・破傷風)、麻しん風しん2期、日本脳炎2期、子宮頸がん予防以外は個別通知を行っていません。接種時期を確認し、忘れないように接種してください。 | ||||||
| 五種混合ワクチンの対象者は、原則四種混合ワクチン又はヒブワクチンを1回も接種していない方です。 ただし、四種混合ワクチンの生産終了等に伴いワクチンの入手が困難な場合は、四種混合ワクチンから五種混合ワクチンへ切り替えて接種した場合も定期接種として取り扱うことが可能です。四種混合ワクチンの接種が完了していない場合は、医師に相談の上、接種した回数に応じ、残りの回数を五種混合ワクチンに切り替えることができます。 |
||||||
| 子宮頸がん予防ワクチンについては、1回目の接種以降、原則同一銘柄の子宮頸がん予防ワクチンを3回接種してください。 | ||||||
予防接種の前に確認すること
三原市の定期予防接種は、医療機関で個別に接種します。生後2か月から3か月※を目安に「予防接種券」、「予診票」及び冊子「予防接種と子どもの健康」をお届けします。
予防接種は種類によって接種する時期や回数、他の予防接種との間隔があります。「予防接種と子どもの健康」をよく読んで必要性や副反応をよく理解し、体調が良いときに接種してください。
※子宮頸がん予防ワクチンについては、接種時期に対象者へ送付します。
外国語版の「予防接種と子どもの健康」は予防接種リサーチセンターのホームページを参照してください。
確認
他のワクチン接種を行った場合は間隔をあけてください。
・生ワクチン(MR、麻しん、風しん、BCG、水痘、おたふくかぜ、ロタウイルスなど)を接種し、次に生ワクチンを接種する場合は、接種した日の翌日から27日以上の間隔をあけてください。
体調や体質によってはワクチン接種ができない場合があります。次の人は接種しないでください。
・明らかに発熱(通常37.5℃以上をいいます。)をしているお子さん
・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん
・その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、ひどいアレルギー反応(アナフィラキシー)を起こしたことがあることが明らかなお子さん
・麻しん(はしか)、風しんの予防接種の対象者で妊娠していることが明らかな人
お子さんには直接関係ない規則ですが、任意で受ける人のことも考慮したものです。
・BCG接種の場合においては、外傷などによるケロイドが認められるお子さん
・その他、医師が不適当な状態と判断した場合
次の人は接種をなるべく控えてください。
・日本脳炎及び子宮頸がん予防ワクチンの対象者のうち13歳以上の女性の接種にあたっては、妊娠の可能性がある人、授乳中の人(医師が特に必要と認めた場合は接種できます)。
次の人はワクチン接種をするか医師と相談してください。
・心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療を受けているお子さん
・予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられたお子さん及び発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられたお子さん
・過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがあるお子さん
・過去に免疫不全の診断がなされているお子さん及び近親者に先天性免疫不全症の人がいるお子さん
・ワクチンにはその製造過程における培養に使う卵の成分、抗生物質、安定剤などが入っているものがあるので、これらにアレルギーがあるといわれたことのあるお子さん
・BCG接種の場合においては、家族に結核患者がいて長期に接触があった場合など、過去に結核に感染している疑いのあるお子さん
予約
医療機関に予約が必要な場合があります。
また、マイナンバーカードを利用したデジタル予防接種(サービス対応医療機関に限ります。)を希望する場合は、予約時にマイナポータルで入力した予診票を利用することをお伝えください。
※サービス対応医療機関等は、リンク先記事「予防接種のデジタル化について」でご確認ください。
接種の際に持参するもの
予防接種券(記入できるところは記入しておいてください。)
予診票(記入できるところは記入しておいてください。)
母子健康手帳
住所と年齢が確認できるもの(健康保険証など)
発熱などで予防接種を行わず治療をする場合がありますので、乳幼児医療費受給資格者証や健康保険証、治療費なども念のため持参してください。
16歳未満のお子様に保護者以外が同伴する場合は委任状 が必要です。
予防接種の後に気をつけること
予防接種を受けたあと30分間程度は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましよう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
・接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
・接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
・接種当日は、激しい運動は避けましょう。
・接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、早くに医師の診察を受けましょう。
副反応について
一般的に予防接種を行うと病気への免疫(抵抗力)がつきますが、発熱などの副反応(ふくはんのう)が発症する場合があります。
主な副反応は注射部位に腫れや痛みの反応や頭痛や発熱・疲労感など全身への反応があります。
また、重い副反応としてまれにアナフィラキシー様症状が現れることがあります。
気になる症状があった場合は医師に相談してください。
健康被害について
三原市に居住する間に予防接種法に基づいて実施された予防接種(定期の予防接種または臨時の予防接種)を受けた方が、疾病にかかり、障害の状態となり、または死亡した場合において、この疾病、障害または死亡がこの予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法による健康被害救済制度及び三原市の予防接種健康被害救済制度に基づいた補償を受けることができます。
また、医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の適用が受けられる場合があります。
気になる症状があった場合は医師にご相談ください。
実施医療機関について
県内の広域化予防接種実施医療機関では予防接種券により無料で接種できます。
三原市外の医療機関での接種を希望される場合は、希望される医療機関で広域化接種実施医療機関であるかを確認してください。県内の広域化接種実施医療機関外または、県外の医療機関での接種を希望される場合は事前の手続きが必要です。
医療機関へのお知らせ
副反応の報告
2013(平成25年)4月1日から予防接種後の副反応を診断した医師等に報告が義務付けられました。副反応を診断した場合は、厚生労働省へ早急にFaxまたは医薬関係者が利用できる電子報告システム(事前の利用登録が必要です。)で報告してください。
また、重篤な健康被害があった場合は三原市の予防接種健康被害救済制度と医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の適用になる場合があります。
| 報告様式・基準 | 副反応報告書・基準(別紙様式1) 副反応報告書記入要領 健康被害報告別記 |
| コッホ現象報告書 | |
| 厚生労働省Fax番号 | 0120-510-355 |
接種時の注意
・予診の際に三原市の定期接種対象者かどうかを母子健康手帳や健康保険証などで確認してください。年齢や回数が対象と外れていた場合は、定期接種の適用外になります。また三原市外に住民票のある方については、住民票のある市区町村へお問い合わせください。
・接種後は母子健康手帳に接種記録を記載してください。
予防接種券の発行について
予防接種券は生後2~3か月頃※にお届けします。他市から転入してきた人や紛失した人は市役所2階こども安心課または保健福祉センターで手続きが必要です。(保健福祉センターへお越しの際は事前に電話連絡をお願いします。)
手続きには母子健康手帳、申請者(保護者等)の本人確認書類が必要です。
また、転出などで三原市民でなくなった場合は三原市の予防接種券は使用できませんので、転出先で接種券の交換等の手続きをしてください。
※子宮頸がん予防ワクチンについては、接種時期に対象者へ送付します。
予防接種券は、他人への譲渡が禁じられています。また、きょうだい間での誤使用に注意してください
| 本郷保健福祉センター | 0848-86-3609 |
| 久井保健福祉センター | 0847-32-8551 |
| 大和保健福祉センター | 0847-34-0960 |