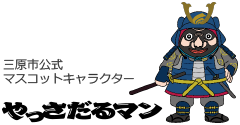本文
三原市パートナーシップ宣誓制度
三原市パートナーシップ宣誓制度(令和4年1月1日制度開始)
『三原市パートナーシップ宣誓制度』は、一方または双方が性的マイノリティでパートナー関係にある二人が、お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合う関係(パートナーシップ)である宣誓書を提出し、市が受領証及び受領カードを交付する制度です。
この受領証及び受領カードによって、三原市の公的なサービスを受けることが一部可能となります。
法的な婚姻の関係を認める制度ではないため、法的効力は発生しませんが、性的マイノリティの方の生きづらさや不安を軽減し、多様性を認め合いながら、誰もが自分らしく暮らせる社会の形成に向けて、本制度を実施するものです。
三原市パートナーシップ宣誓制度シンボルマーク

三原市が性的マイノリティの方々をサポートするとともに、市民が性の多様性を理解し、人権が守られ、それぞれの生き方が尊重される社会をめざし、性の多様性を表す6色の色彩(レインボーカラー)と、広がる可能性の象徴としての「羽」、人権の「人の文字」をモチーフにデザインしています。
三原市パートナーシップ宣誓制度シンボルマーク [その他のファイル/137KB]
性的マイノリティとは
性的指向や性自認において、「性」のあり方が少数派であると認められる場合をいいます。ある民間の調査によると国内で8.9%(11人に1人程度)が性的マイノリティに該当するという結果も出ています。特にLGBTQ+は性的マイノリティの総称の一つとしてよく用いられます。
LGBTQ+とは
| L | レズビアン | 女性を好きになる女性 |
|---|---|---|
| G | ゲイ | 男性を好きになる男性 |
| B | バイセクシュアル | 男女どちらも好きになる人 |
| T | トランスジェンダー | 心と体の性が一致しない人 |
| Q | クエスチョニングなど | 自分の性的指向や性自認が分からない人 |
| + | プラス | さらにさまざまな性があるという意味 |
制度を利用できる方(要件)
一方または双方が性的マイノリティである人で、次のすべてに当てはまるお二人
- 成年に達していること
- いずれか一方若しくは双方が市内に住所を有していること、または宣誓の日から原則として14日以内に市内への転入を予定していること。
- 配偶者(事実婚を含む)がいないこと
- 宣誓者以外の者とパートナーシップの宣誓をしていないこと
- 宣誓者同士が近親者でないこと(養子縁組を除く)
手続の流れ
(1) 事前申し込み
宣誓したい日の原則10日前までに、電話・メール・申し込みフォームで事前にご来庁のご予約をお願いします。
電話・メールでの申し込みの際は、予約時に以下のことをお伝えください。
- お二人の氏名、生年月日、住所
- 希望日時
- 日中連絡のとれる電話番号・メールアドレス
問い合わせは三原市人権推進課まで
Tel 0848-67-6044
Mail jinken@city.mihara.hiroshima.jp
(2) 必要書類の提出
必要書類を三原市人権推進課まで持参もしくは郵送ください。(電子申請で添付された方は提出不要)
【必要書類】
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- 戸籍抄本または配偶者がいないことを証明できる書類(独身証明書など)
- (三原市に転入予定の場合)転出証明書やアパートの契約書の写しなど
(3) 必要書類の確認
要件を満たしているかどうか確認し、不備等がなければ届出を受理します。
宣誓日時を調整し、連絡します。
(4) 宣誓書への署名(個室対応)
お二人で三原市役所にご来庁いただき、宣誓書へ署名いただきます。
本人確認できる写真付きの書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。
(5) 受領証・受領カードの交付
宣誓書の提出後、パートナーシップ宣誓書受領証・受領カードを交付します。
当日交付出来ない場合は、後日簡易書留で受領証等を送付します。
交付される書類
(1) パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)
(2) パートナーシップ宣誓書受領カード(運転免許証サイズ)
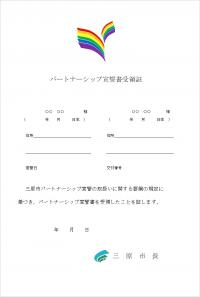

(イメージ)パートナーシップ宣誓書受領証・受領カード [PDFファイル/135KB]
※デザインは変更される場合があります
他の自治体との相互利用
・広島市(令和4年1月1日相互利用開始)
広島市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
・安芸高田市(令和4年1月1日相互利用開始)
安芸高田市パートナーシップ制度<外部リンク>
・廿日市市(令和4年4月1日相互利用開始)
廿日市市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
・府中町(令和4年4月1日相互利用開始)
府中町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
・海田町(令和4年10月1日相互利用開始)
海田町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
・三次市(令和5年1月1日相互利用開始)
三次市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
・東広島市(令和5年4月1日相互利用開始)
東広島市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
・府中市(令和5年10月1日相互利用開始)
府中市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
・北広島町(令和6年4月1日相互利用開始)
北広島町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
・庄原市(令和6年4月1日相互利用開始)
庄原市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
・安芸太田町(令和7年4月1日相互利用開始)
安芸太田町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
・世羅町(令和7年4月1日相互利用開始)
世羅町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
・大竹市(令和7年10月1日相互利用開始)
大竹市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
宣誓書受領証の提示により受けられるサービス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 市営住宅 | 市営住宅の入居者要件で同居人として認められます。 |
| 記念樹の贈呈 | パートナーシップ宣誓された方に記念樹を贈呈します。 |
| 身体障害者等に対する軽自動車税減免 | 身体障害者等、またはそのパートナーが所有する軽自動車等の自動車税を申請により減免します。 |
| ファーストマイホーム応援事業補助金 | 市内において新たに住宅を取得する若年層世帯に補助金を交付します。 |
| 新婚世帯生活支援補助金 | 新婚世帯に住居費(住宅の取得費用・リフォーム費用・賃借費用)、引越費用の補助金を交付します。 |
| 犯罪被害者等見舞金 | 犯罪行為によりパートナーが死亡した場合、遺族見舞金の支給申請ができます。 |
| 被災(り災)証明書 | 災害により被害をうけた程度を証明するものです。(火災に起因するものを除く) |
- 受領証の掲示で利用可能となる三原市行政サービス [PDFファイル/57KB]
- パートナーシップ宣誓しなくても既に利用可能な三原市行政サービス [PDFファイル/52KB]
- 広島県の利用可能な行政サービス等一覧 〈外部リンク〉
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通信 | 携帯電話の家族割にパートナーを適用できる。 |
| 金融 | パートナーと共同で住宅ローンが組めるようになる。 |
| 保険 | パートナーを生命保険の受取人に指定できる。 |
| 医療 | パートナーが家族として認められ、面会や手術同意書に署名ができる。 |
| 住居 | パートナーと一緒に不動産契約ができる。 |
| 福利厚生 | パートナーとの関係において、結婚祝金、結婚休暇、看護休暇、介護休暇、介護休業、忌引休暇などを受けられる。 |
※個別のサービスについては各事業者にお問い合わせください。
宣誓件数 (令和8年1月1日時点)
3件
留意事項
- 受領証を紛失、毀損、汚損した際は、再交付の申請ができます。
- 受領証発行による手数料はかかりません。(必要書類の発行手数料は自己負担です。)
- 受領証は法的な効力を有するものではありません。
- プライバシーに最大限配慮し、宣誓の場所については個室をご用意します。
- 受領書、受領カードに記入するお名前には通称名をご使用いただけます。
- 職場などへの提出のため、パートナーシップ宣誓書の記載内容等証明書を発行できます。
三原市パートナーシップ宣誓制度 よくある質問 [PDFファイル/289KB]
関連資料のダウンロード
悩み相談
相談は無料です 秘密は守られます
「人権相談」
市役所3階 人権推進課 相談室
0848-67-6044 (毎週月~金曜日 10時~16時 ※祝日・年末年始は除く)
人権相談員が対面または電話により相談に応じています。
「LGBT電話相談」
082-207-3130 (毎週土曜日 10時~16時 ※祝日・年末年始は除く)
相談内容(例)
- 自分の性別がよくわからない
- 同性を好きになった、どうしよう
- 家族や友人から打ち明けられた など
ご家族、パートナー、支援者からの相談も受け付けています。