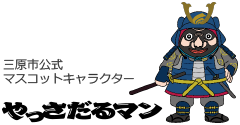本文
よくある問い合わせについて(高齢者帯状疱疹)
よくあるお問い合わせ
Q1)家族には市役所から帯状疱疹ワクチン接種の案内が郵送で届きましたが、私には届いていません。
どうして届かないのでしょうか?
私も帯状疱疹ワクチン接種を受けることはできますか?
Q2)私は今、帯状疱疹ワクチンの定期接種の対象年齢ですが、三原市から案内が届いていません。
どうしてですか?
Q3)帯状疱疹ワクチン接種の薬は、生ワクチン(ビケン)と組み換えワクチン(シングリックス)があるようなのですが、どちらが良いのですか?
Q4)過去に帯状疱疹ワクチン接種を任意で接種したことがありますが、今回、定期接種や助成事業で接種することは可能でしょうか?
Q5)帯状疱疹ワクチン接種の申請手続きは、市役所に行かないと出来ませんか?
Q6)帯状疱疹ワクチン接種の申請手続きには、何を持参すればいいですか?
Q7)以前、帯状疱疹になったのですが、免疫ができているので接種しなくても大丈夫でしょうか?
Q8)今年度、帯状疱疹ワクチン定期接種の対象となっていますが、5年後再び接種の機会があるので、今年度は接種しなくてもいいのでしょうか?
Q9)帯状疱疹ワクチン接種の定期接種の対象者です。市役所から送られた文書を持参して医療機関に行けばいいのでしょうか。他に必要は手続きはありませんか?
Q10)帯状疱疹ワクチン定期接種の対象者は、無料で接種ができますか?
Q11)どのような状況であれば、ワクチン接種が無料になりますか?
Q12)組み換えワクチン(シングリックス)の接種間隔について、2ヶ月が無理なので3ヶ月空けてもいいですか?
Q13)定期接種または助成事業で生ワクチンを接種した場合、再接種は必要ですか?
Q14)全額自己負担で接種する場合は、接種費用はどのくらいかかりますか?
Q15)帯状疱疹ワクチンは他のワクチンと同時に接種できますか?
Q1)家族には市役所から帯状疱疹ワクチン接種の案内が郵送で届きましたが、私には届いていません。
どうして届かないのでしょうか?
私も帯状疱疹ワクチン接種を受けることはできますか?
A1)今年度、帯状疱疹ワクチン接種の定期接種対象者に対して、今年4月に市役所から文書をお送りしています。定期接種の対象とならない66歳以上の人は、三原市独自で行っている助成事業の対象となりますので、申請していただくことで、定期接種の対象者と同様にワクチン接種を受けることができます。助成事業は令和8年3月31日までです。
助成事業の詳細については、こちらをご覧ください。
なお、助成事業をご利用の場合は、定期接種の対象年度になっても市役所からの案内はありませんので、ご承知ください。
Q2)私は今、帯状疱疹ワクチンの定期接種の対象年齢ですが、三原市から案内が届いていません。
どうしてですか?
A2)今年度の定期接種は、令和7年4月2日から令和8年4月1日の間に、65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳以上となる方が対象となります。
生年月日がこの期間内に該当するかをご確認ください。また、定期接種の対象者以外でも、今年度に接種を希望される人は、助成事業をご利用ください。
助成事業の詳細については、こちらをご覧ください。
Q3)帯状疱疹ワクチン接種の薬は、生ワクチン(ビケン)と組み換えワクチン(シングリックス)があるようなのですが、どちらが良いのですか?
A3)生ワクチンと組み換えワクチンは、接種回数・接種費用・予防効果の持続期間・接種後の副反応等において違いがあります。持病がある人は、その症状等により生ワクチンが接種できない場合もあるため、自分に合ったワクチンを選ぶことが重要です。
不安な場合は、主治医にご相談することをお勧めします。
生ワクチンと組み換えワクチンについて、詳しくはこちらをご覧ください。
Q4)過去に帯状疱疹ワクチン接種を任意で接種したことがありますが、今回、定期接種や助成事業で接種することは可能でしょうか?
A4)過去に帯状疱疹ワクチンを接種した人は、過去の接種から年月が経過し、発症予防効果が低下している場合、医師が接種の必要があると判断すれば、接種が可能ですので、かかりつけ医にご相談ください。
Q5)帯状疱疹ワクチン接種の申請手続きは、市役所に行かないと出来ませんか?
A5) 市役所窓口まで来なくても、三原市のホームページから申請できます。また郵送での申請も可能ですので、ご活用ください。
定期接種の申請について詳しくは、こちらをご覧ください
助成事業の申請について詳しくは、こちらをご覧ください
Q6)帯状疱疹ワクチン接種の申請手続きには、何を持参すればいいですか?
A6) 次のとおり、誰が申請するかによって異なりますので、ご注意ください。
(1) 被接種者本人が申請する場合…マイナンバーカード等の本人確認書類が必要です。
(2) 同一世帯のご家族が代理で申請する場合:
「定期接種」の場合…申請者(ご家族)の本人確認書類が必要です。
「助成事業」の場合…被接種者の本人確認書類と認印が必要です。
(3) 別世帯のご家族が代理で申請する場合:
「定期接種」の場合…申請者(ご家族)の本人確認書類と被接種者の認印が必要です。
「助成事業」の場合…被接種者の本人確認書類と認印が必要です。
なお、定期接種で申請手続きが必要なのは、市外医療機関で接種する人と、接種費用が無料になる市県民税非課税世帯または生活保護世帯の人です。
Q7)以前、帯状疱疹になったのですが、免疫ができているので接種しなくても大丈夫でしょうか?
A7)帯状疱疹は、過去に水疱瘡に感染したことのある人が、免疫能の低下により発症する病気です。体内にはウイルスが残っており、帯状疱疹の症状が収まっても、免疫機能が低下すると再発する可能性があります。
Q8)今年度、帯状疱疹ワクチン定期接種の対象となっていますが、5年後再び接種の機会があるので、今年度は接種しなくてもいいのでしょうか?
A8) 定期接種の機会は生涯で1回限りであり、5年後にその機会はありません。希望される人は、今年度中にワクチンを接種してください。
帯状疱疹の定期予防接種は65歳の人を対象としています。令和7年度から令和11年度までの5年間、65歳以上の人全員に定期接種の機会を設けるため、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳になる人(令和7年度は100歳以上も対象)も定期接種の対象になります。令和12年度からは、65歳の人のみが定期接種の対象者となります。
Q9)帯状疱疹ワクチン接種の定期接種の対象者です。市役所から送られた文書を持参して医療機関に行けばいいのでしょうか。他に必要は手続きはありませんか?
A9) 今年度、市県民税が課税世帯の人については、お送りした封筒と案内文書を医療機関に持参することで助成が受けられますので、手続きは必要ありません。ただし、市民税非課税世帯と生活保護世帯の人は接種費用が無料となりますので、接種する前に市役所や各保健福祉センターの窓口、またはインターネットや郵送で申請してください。審査後、申請者に患者負担額が0円と記載された接種券と予診票を交付しますので、医療機関に提出してください。また、インターネットおよび郵送で申請された人には、審査後に市役所から郵送します。接種後の払戻し等はできませんので、必ず事前に申請手続きをお願いします。
なお、各医療機関で常に予防接種が受けられるわけではありませんので、事前に医療機関へお問い合わせいただくことをお勧めします。
Q10)帯状疱疹ワクチン定期接種の対象者は、無料で接種ができますか?
A10)今年度、市県民税が課税されている人は、接種費用の一部を負担する必要があります。被接種者を含む世帯員全員の市県民税が非課税であれば、無料で接種を受けることができます。申請は、市役所または各保健福祉センターに直接お越しいただくか、インターネットまたは郵送で行ってください。
Q11)どのような状況であれば、ワクチン接種が無料になりますか?
A11)定期接種や助成事業に関わらず、接種費用については、申請時に世帯員の市県民税が課税されているかどうかで判断しています。
Q12)組み換えワクチン(シングリックス)の接種間隔について、2ヶ月が無理なので3ヶ月空けてもいいですか?
A12) 組み換えワクチン(シングリックス)の接種間隔は、標準で2ヶ月とされています。しかし、2ヶ月で接種できない場合は、6ヶ月以内に接種してください。また、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1ヶ月まで短縮することができます。
定期接種・助成事業ともに2回目の接種を令和8年3月31日までに終えてください。
Q13)定期接種または助成事業で生ワクチンを接種した場合、再接種は必要ですか?
A13) 生ワクチンの予防効果は、接種から5年後には約40%程度となり、10年後までにほとんど予防効果がなくなるといわれています。主治医が再接種の必要あると判断した場合は、検討してください。ただし、市の助成は生涯1回限りのため、接種費用は全額自己負担となります。
Q14)全額自己負担で接種する場合は、接種費用はどのくらいかかりますか?
A14) 任意接種のため、接種費用は医療機関ごとに設定されています。一般的に、生ワクチンは8,000円以上、組換えワクチンは1回20,000円以上、2回接種で計40,000円以上かかります。
Q15)帯状疱疹ワクチンは他のワクチンと同時に接種できますか?
A15) 医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザや肺炎球菌、新型コロナウイルスワクチンと同時に接種することが可能です。ただし、生ワクチン(ビケン)を接種する場合は、他の生ワクチンとの同時接種はできませんので、27日以上の間隔を置いて接種してください。