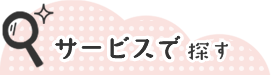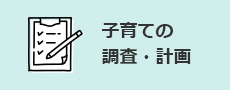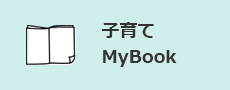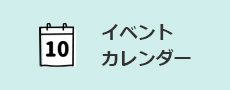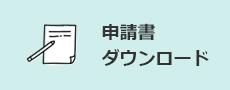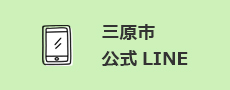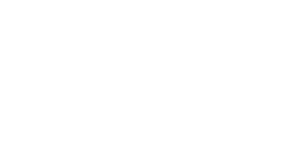本文
幼児教育・保育の無償化
目次
・幼児教育・保育の無償化とは
・対象者と無償化対象の一覧表
・無償化となる利用形態
・よくある質問
・様式集
幼児教育・保育の無償化とは
幼児教育・保育の無償化とは、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの児童と、住民税非課税世帯の0歳児クラス~2歳児クラスまでの児童の利用料が無償化される制度です。
※第2子以降の保育料無償化についてはこちらへ
対象者と無償化対象の一覧表
| 利用施設・事業 |
0~2歳児クラス |
3~5歳児クラス | 手続き 問い合わせ先 |
|
|
保育所・園 認定こども園 小規模保育事業等 |
無償 | 無償 |
不要 問い合わせ先 |
|
|
認定こども園 私立幼稚園 |
教育 | - | 無償 |
不要 問い合わせ先 |
| 預かり 保育 |
満3歳児は |
日額450円、月額11,300円 |
保育の必要性の認定申請 問い合わせ先 |
|
| 公立幼稚園 | 教育 | - | 無償 |
不要 問い合わせ先 |
|
私立幼稚園 国立大学 特別支援学校 |
教育 | - | 月額25,700円 まで無償 |
不要 問い合わせ先 |
| 預かり 保育 |
- |
日額450円、月額11,300円 |
保育の必要性の認定申請 問い合わせ先 |
|
|
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業等 |
月額42,000円 まで無償 |
月額37,000円 まで無償 |
保育の必要性の認定申請 問い合わせ先 |
|
| 障害児通園施設 | 無償 | 無償 |
不要 問い合わせ先 |
|
※国立大学附属幼稚園の無償化上限額については、教育振興課(Tel0848-67-6060)に問い合わせてください。
無償化となる利用形態
認可保育施設や幼稚園等を利用している場合
対象施設
・保育所
・幼稚園(新制度移行済)
・認定こども園
・地域型保育事業
無償化の内容
・3~5歳児クラスの子 全員の利用料が無料(給食費等は対象外)
・満3歳児の1号認定の子 全員の利用料が無料(給食費等は対象外)
・0~2歳児クラスの子 非課税世帯の場合は保育料が無料
※0~2歳児クラスの子が第2子以降の場合は、市独自の制度で無償化対象となります。詳しくはこちらへ
認可外保育施設等を利用している場合
認可外保育施設や一時預かり、病児保育などを利用した保育料をお返しします。
※利用日より前に保育の必要性の認定を受ける必要があります。
無償化の上限額
- 3~5歳児クラスの子 最大月37,000円
- 住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子 最大月42,000円
※日用品・文房具費、行事参加費、食材料費、通園送迎費等は無償化対象外。
対象施設等
・対象の認可外保育施設
・一時預かり事業
・ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの活動は対象外)
・病児保育
市内の無償化対象施設・サービスはこちらをご確認ください [PDFファイル/75KB]
※市外の施設を利用する場合は、施設所在地の自治体に無償化対象施設かご確認ください。
対象者
次のすべてに該当する子
〇保護者全員が、保育の必要性の事由に該当する
〇認可保育所・認定こども園・地域型保育事業等に在園していない子
※幼稚園に在園している場合は、状況により異なります。
〇無償化の対象となる認可外保育施設等を利用中または利用予定の子
〇0~2歳児クラスの子は住民税非課税世帯であること
※住民税課税世帯であっても対象のお子さんが、生計を同一とする第2子以降の子である場合は、市独自の制度で無償化対象となります。詳しくはこちらへ
お子さんが無償化の対象かフロー図でも確認できます [PDFファイル/74KB]
施設の利用前に手続きが必要です
利用料を請求するためには、利用日以前に保育の必要性の認定申請が必要です。事前にこども保育課(市役所本庁2階)へ、保育の必要性が確認できる書類と合わせて「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」を提出してください。
〇申請様式:子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」[PDFファイル/482KB]
【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル/844KB]
理由書 [PDFファイル/38KB](認可外保育施設利用者のみ)
〇保育の必要性が確認できる添付書類の様式はこちらへ
※その他、課税証明書、戸籍謄本などが必要な場合があります。
請求の流れ
1.施設へ保育料(利用料)を支払う
2.施設から特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼支援提供証明書を受領する
3.施設等利用費請求書に、記入例を参考に必要事項を記入する
※請求書は自書でない場合は、押印が必要です。
4. 上記の2、3の書類をこども保育課(市役所本庁2階)へ
※初回の請求または振込先口座を変更する場合は通帳等の写しも必要です。
5.市から請求書に記載された銀行口座へ振込み
請求期限:施設を利用月の翌年度の4月末まで
例1)令和8年3月利用分 → 請求期限:令和8年4月末
例2)令和8年4月利用分 → 請求期限:令和9年4月末
幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用している場合
幼稚園や認定こども園に通う1号認定の子が、預かり保育を利用た場合に、利用実態に応じて預かり保育料をお返しします。
※保育料を請求するには、利用日より前に、市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
対象施設
・幼稚園
・認定こども園(幼稚園部分)
無償化の上限額
- 3~5歳児クラスの子 最大月11,300円(一日450円)
- 住民税非課税世帯の満3歳児クラスの子 最大月16,300円(一日450円)
※日用品・文房具費、行事参加費、食材料費、通園送迎費等は無償化対象外です。
対象者
次のすべてに該当する子。
〇保護者全員が、保育の必要性の事由に該当する
〇幼稚園または認定こども園の幼稚園部分に在籍し、預かり保育を利用(または利用を予定)である
〇在籍している幼稚園または認定こども園が平日8時間以上かつ、年間200日以上の預かり保育を実施している
〇満3歳児の子は住民税非課税世帯である
※住民税課税世帯であっても対象のお子さんが、生計を同一とする第2子以降の子である場合は、市独自の制度で無償化対象となります。詳しくはこちらへ
施設の利用前に申請手続きが必要です
利用料を請求するためには、利用日以前に保育の必要性の認定申請が必要です。施設の利用日より前に市役所へ、保育の必要性が確認できる書類と合わせて「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」を下記提出先へ。
【提出先】
・幼保連携型認定こども園の預かり保育を利用する場合 → こども保育課(市役所本庁2階)へ
・幼稚園型認定こども園の預かり保育を利用する場合 → 教育振興課(市役所本庁6階)へ
※みどり幼稚園、皆実みどり幼稚園、私立幼稚園昭和園、糸崎幼稚園で預かり保育を利用する場合は、各園へ提出してください。
〇申請様式:子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 【記入例】
〇保育の必要性が確認できる添付書類の様式はこちらへ
請求の流れ
【償還払いを受ける場合】
1.施設へ預かり保育料(利用料)を支払う
2.施設から特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼支援提供証明書を受領する
3.施設等利用費請求書に、記入例を参考に必要事項を記入する
※請求書は自書でない場合は、押印が必要です。
4. 上記の2、3の書類をこども保育課(市役所本庁2階)へ(初回の請求または振込先口座を変更する場合は通帳等の写しも必要です。)
5.市から請求書に記載された銀行口座へ振込み
6. 請求期限:施設を利用した月の翌年度の4月末まで
例1)令和8年3月利用分 → 請求期限:令和8年4月末
例2)令和8年4月利用分 → 請求期限:令和9年4月末
【園が法定代理受領する場合】
法定代理受領とは、各施設が保護者に代わって三原市へ請求し支払いを受ける制度です。下記施設は法定代理受領の対象となっていますので、請求手続きの要否については各園に確認してください。
〇市内の法定代理受領対象施設
認定けいこうこども園、さんさんまりんこども園、認定こども園月見幼稚園、みどり幼稚園、皆実みどり幼稚園、私立幼稚園昭和園、糸崎幼稚園
よくある質問
Q1 無償化の手続きは必要ですか?
利用している施設やご家庭の状況により、無償化の対象になるための申請手続きが必要です。
☆ 手続きが不要な場合
- 保育所・認定こども園(保育認定)・小規模保育事業所等に入園している場合
- 認定こども園(教育認定)に入園していて、預かり保育を利用しない(保育の必要性がない)場合
☆ 手続きが必要な場合
- 一定基準以上の預かり保育を実施している幼稚園、認定こども園(教育認定)に入園していて、
預かり保育を利用する(保育の必要性がある)場合 - 一定基準以上の預かり保育を実施していない幼稚園に入園している場合
- 認可外保育施設等を利用している場合
Q2 「保育の必要性の認定」をもらうためには何が必要ですか?
手続きには、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」 と、保育の必要性を証明する「添付書類」が必要です。 添付書類は、ひとり親世帯でなければ、父・母両方のものが必要になります。
- 「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」 [PDFファイル/482KB]
- 【記入例】認可外保育施設等の利用の場合 [PDFファイル/844KB]
- 【記入例】認定こども園1号認定で預かり保育を利用の場合 [PDFファイル/804KB]
Q3 無償化の対象にならない費用は、どのようなものがありますか?
給食費(食材料費)、行事費、通園送迎費などは、無償化の対象になりません。引き続き実費を徴収いたします。
Q4 病児保育・一時預かり・ファミリーサポートセンター事業は無償化の対象ですか?
保育所・認定こども園(保育認定)・小規模保育事業所等に入園している場合は、対象になりません。
入園されていない方で、無償化の対象になるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
Q5 満3歳児と3歳児はどう違うのですか?
満3歳児とは今年度3歳の誕生日を迎えたお子さんのことを言います。3歳児は今年度の初めに、既に3歳を迎えている子を言います。
様式集
保育の必要性の認定申請に必要な書類
- 「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」 [PDFファイル/482KB]
- 【記入例】認可外保育施設等の利用の場合 [PDFファイル/844KB]
- 【記入例】認定こども園1号認定で預かり保育を利用の場合 [PDFファイル/804KB]
- 理由書 [PDFファイル/38KB](認可外保育施設利用者のみ)
保育の必要性を確認するための添付書類
| 保育が必要な理由 | 添付書類の例 | |
| 就労・就学 | 居宅外就労(予定含む) | 就労証明書 [PDFファイル/152KB] |
| 自営業・農業 |
営業所得が確認できる直近の確定申告書または市民税申告書の写し |
|
| 学生 |
在学証明書もしくは学生証の写し |
|
|
妊娠・出産 (認定期間:出産予定月とその前後1か月以内) |
母子手帳の写し(母の氏名と出産予定日を確認します) |
|
| 保護者の疾病・障害 |
医師の診断書、障害者手帳の写し、介護保険証の写し等 ◎その他保育ができない状況に応じて書類を提出していただく場合があります。 |
|
| 病気等の看護 |
介護(看護)状況申告書(様式5) [PDFファイル/58KB] 医師の診断書、障害者手帳の写し、介護保険証の写し等 |
|
| 就労予定 | ||
|
求職活動 (認定期間:3か月以内) |
申立書(様式3) [PDFファイル/70KB] | |
※下線がある添付書類は、市の様式を利用してください。
保育の必要性についての具体的な内容は、 「保育所(園)入所申込について」の1P「保育所に入所できる基準」をご覧ください。
請求時に必要な書類
- 施設等利用費請求書(認可外保育施設等) [PDFファイル/171KB] 【記入例】 [PDFファイル/237KB]
- 施設等利用費請求書(預かり保育用) [PDFファイル/146KB] 【記入例】 [PDFファイル/804KB]
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼支援提供証明書 [PDFファイル/68KB](施設が記入)
※請求書は自書でない場合は押印が必要です。
※初めて請求するときは振込先口座の通帳等の写しも必要です。
参考
幼児教育・保育の無償化について