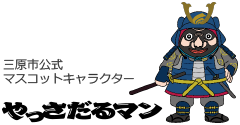本文
くりぶね(約600年前の船底材)
| 名称 | 沼田東出土中世船の船底材 |
| かな | ぬたひがししゅつどちゅうせいせんのせんていざい |
 |
|
| 時代 | 室町時代(1336~1573)か |
| 場所 |
三原市沼田東町七宝(ぬたひがしちょうしっぽう) 郷中川(ごうちゅうがわ)出土 |
| 調査次 | 昭和50(1975)年1月 |
| 材質 | ムクノキ |
| 員数 | 1 |
| 寸法 | 縦690.0×横90.0×高50.0(cm) |
| 指定 | 市指定重要有形文化財 |
| 指定日 | 昭和56(1981)年10月21日 |
| 所蔵 | 三原市歴史民俗資料館 |
| 概要 |
昭和50(1975)年1月、県のほ場整備事業中に郷中川の川底約1メートルの所から見つかりました。この船は一本の丸太を半分に割り、割った方をくりぬいて船の形にしました。側面には手斧の跡が残っていたり、釘が打ち込まれていたりと手が加えられています。室町時代の船の構造を知ることができる貴重な資料です。『三原市史 第1巻 通史編1』第286図,図版74。
|