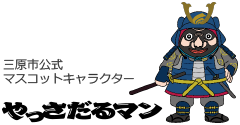本文
食品ロスの削減に取り組みましょう
「食品ロス」とは,まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。
日本では、年間2,759万トン(※)の食品廃棄物等が出されています。このうち、「食品ロス」は643万トン(※)にもなります。
これは、食品ロスを国民一人当たりに換算すると"お茶腕約1杯分(約139g)の食べもの"が毎日捨てられていることになります。
大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮から、食品ロスを減らすことが必要です。
(※)農林水産省「食品ロス量(令和2年度推計値)の公表」についてより
日本で発生している「食品ロス」では、飲食店等における食べ残しによるものが多く発生しています。
このような飲食店等における「食品ロス」の削減に向けて、食べきり運動や自己責任を前提に食べ残し料理の持ち帰りを行いましょう。
食べきりの促進
持ち帰る前に消費者・飲食店それぞれの立場から食べきりの取組を促進することにより、「食べ残し」の削減を進めましょう。
消費者の方へ
飲食店等で食事をする時は
・出来たての最も美味しい状態で提供された料理を食べましょう。
・自分自身の食事の適正量を知り、食べきれると思う量を注文するようにしましょう。
・小盛りや小分けメニューを上手に活用しましょう。お店選びの際にも、こうしたメニューを設定しているお店を選ぶことを考慮しましょう。
・食べ放題のお店では、元を取るために無理をして皿に盛りつけることや、食べ残すことはやめましょう。
飲食店の方へ
・お客様の食べ残しは、廃棄することになり飲食店にとっても損失となるものです。食べきっていただくように料理を出すタイミングや客層に応じた工夫をしましょう。
・お客様が食事量の調整・選択ができるように、小盛りや小分けの商品をメニューに採用しましょう。
・宴会等大量の食事を準備する際には、食べ残しが発生しないよう幹事と食事量やメニューを相談しましょう。
・宴会等において、お客が食べきったらサービス券を配付するなど、食べきることに意欲を持たせることも方法の一つです。
食べ残し料理の「持ち帰り」は自己責任の範囲で
飲食店等で提供され、数時間常温に置かれた食べ残し料理は、提供後すぐの状態の料理と比較して食中毒リスクが高まります。食べ残し料理を持ち帰る場合は、食中毒リスクを十分に理解した上で自己責任の範囲で行うようにしましょう。
消費者の方へ
・持ち帰りは、刺身などの生ものや半生など加熱が不十分なものは避け、帰宅後に加熱が可能なものにし、食べきれる量を考えて行いましょう。
・自ら料理を詰める場合は、手を清潔に洗ってから清潔な容器に清潔な箸などを使って入れましょう。また、水分はできるだけ切り、早く冷えるように浅い容器に小分けしましょう。
・料理は暖かい所に置かないようにしましょう。
・時間が経過することにより食中毒のリスクが高まるので、寄り道をしないようにしましょう。また、帰宅までに時間がかかる場合は、持ち帰りはやめましょう。
・持ち帰った料理は帰宅後できるだけ早く食べるようにしましょう。
・中心部まで十分に再加熱してから食べましょう。
・少しでも怪しいと思ったら、口に入れないようにしましょう。
飲食店の方へ
・持ち帰りの希望者には、食中毒等のリスクや取扱方法等、衛生上の注意事項を十分に説明しましょう。
・持ち帰りには十分に加熱された食品を提供し、生ものや半生など加熱が不十分な料理は希望者からの要望があっても応じないようにしましょう。
・清潔な容器に清潔な箸などを使って入れましょう。水分はできるだけ切り、残った食品が早く冷えるように浅い容器に小分けしましょう。
・外気温が高い時は持ち帰りを休止するか、保冷剤を提供しましょう。
・その他、料理の取り扱いについて注意書きを添えるなど、食中毒等の予防をするための工夫をしましょう。
外部リンク
上記のほかにも、家での食品の保管方法を見直したり商品棚手前の値引き商品などから購入する「てまえどり」を行うことで、「食品ロス」を削減することができます。
日常生活の中でひとりひとりができることから「食品ロス」の削減に取り組みましょう。