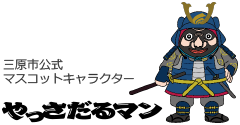本文
【食品ロス削減】食べ残し「持ち帰り」の際の注意事項
食べ残し「持ち帰り」の際の注意事項
外食時の食品ロスを減らすためには、食べきれる量だけ注文することが大前提ですが、やむなく食べ残しが発生してしまったときは、「持ち帰り」ができるかどうか飲食店に確認してください。
「持ち帰り」に関しては、消費者と飲食店の双方が安心して「持ち帰り」を実施できるよう、注意事項をまとめていますので、よく理解した上で「持ち帰り」を行ってください。
また、食べ残しの「持ち帰り」は国も促進しています。
詳しい内容は次の資料をご参照ください。
「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~(概要)」 [PDFファイル/387KB]
「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~」 [PDFファイル/1.69MB]
注意事項
消費者の方へ
・料理がテーブルの上に提供されてから常温で置かれた状態になり、時間の経過によって、提供後すぐの料理と比較すると食中毒が生じる可能性があることを理解しましょう。
・生ものなどは持ち帰らないようにし、水分含有量が少ない食品や帰宅後に再加熱が可能な食品を持ち帰るようにしましょう。
・料理を移し替える際には、清潔な手で、飲食店の指定する清潔な容器や箸などを使用しましょう。
・時間が経過することにより、食中毒の生じる可能性が高まるので、寄り道はせず、気温の高い日や帰宅までに時間がかかる場合は持ち帰るのをやめましょう。
・帰宅後できるだけ早く食べるようにしましょう。
・中心部まで十分に再加熱してから食べましょう。
・見た目やにおいなど、少しでもおかしいと思ったら、口に入れるのはやめましょう。
・自身で食べずにご家族等に譲渡する場合は、飲食店から説明された注意事項を譲渡する人にも説明しましょう。また、食物アレルギーがある人へは譲渡しないでください。
飲食店の方へ
・持ち帰りの希望者には、食中毒のリスクや取扱方法等、衛生上の注意事項を十分に説明しましょう。
・持ち帰りは十分に加熱された食品とし、生ものや半生など加熱が不十分な食品は、希望者からの要望があっても応じないようにしましょう。
・外気温が高い時は持ち帰りを休止するか、保冷剤を提供しましょう。
・持ち帰りの容器は衛生的に保管した物を飲食店が提供しましょう。
・容器への移し替えは、原則、持ち帰る消費者に実施させましょう。
・可能であれば、注意書きを渡すことや、持ち帰りの容器などに注意事項などを記載する工夫をしましょう。