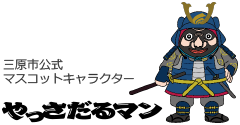本文
医療費が高額になったとき(高額療養費制度)
高額療養費
国民健康保険へ加入されている方が、1か月(診療月ごと)の自己負担限度額を超えて医療費を自己負担(保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額は除く)された場合、自己負担限度額を超えた額が、世帯主からの申請により高額療養費として支給されます。
この高額療養費は、診療を受けた月の翌月1日(ただし、診療を受けた月の翌月以降に自己負担額を支払った場合は、支払った日の翌日)から2年以内であれば、いつでも支給申請ができます。(2年を過ぎると申請できません。)
なお、高額療養費に該当する場合には、診療月の3か月後に市役所から支給申請のお知らせをお送りしますので、次のものをお持ちいただき、申請の手続きをお願いいたします。(※このお知らせの文書が届いた場合には、受給権の消滅時効が中断するため、その後2年間は支給申請の手続きができます。)
※令和5年1月から、世帯主の希望により一度申請すれば、次回以降の申請が不要になり、自動的に指定の口座に振り込まれる「支給申請の簡素化 [PDFファイル/111KB]」ができるようになりました。ただし、簡素化後、振込口座の変更を希望される場合には、届出が必要です。また簡素化停止を希望される場合にも、届出が必要です。
国民健康保険高額療養費支給申請手続き簡素化による振込先口座変更届 [PDFファイル/89KB]
※世帯主の口座に限ります。届出の際には、変更後の預貯金通帳も一緒にご持参ください。
※現在、公金受取口座は利用できません。ご了承ください。
国民健康保険高額療養費支給申請手続き簡素化停止届 [PDFファイル/66KB]
|
【高額療養費の申請に必要なもの】
(注意事項)
|
自己負担限度額(月額)
【70歳未満の人の場合】
| 所得区分 | 総所得金額等(※1) | 適用区分 | 過去12ヶ月間で3回目まで | 4回目以降(※2) |
|---|---|---|---|---|
| 上位所得者 | 901万円超 | ア | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 140,100円 |
| 600万円超 901万円以下 |
イ | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 93,000円 | |
| 一般 | 210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 44,400円 |
| 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | ||
| 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 | |
※1 … 総所得金額等=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(33万円)
※2 … 過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回目以上のときに適用します。所得の申告がない場合は上位所得者とみなされ、区分「ア」になります。
【70歳以上75歳未満の人の場合】
| 所得区分 (住民税課税所得区分) |
適用区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住 民 税 課 税 世 帯 |
課税所得 690万円以上 |
現 役 並 み 所 得 者 |
現役並みIII | 252,600円 (+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
|
| 多数回該当の場合は140,100円 (※2) | |||||
| 課税所得 380万円以上 690万円未満 |
現役並みII | 167,400円 (+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
|||
| 多数回該当の場合は 93,000円 (※2) | |||||
| 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
現役並みI | 80,100円 (+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
|||
| 多数回該当の場合は 44,400円 (※2) | |||||
| 課税所得 145万円未満 |
一般 | 18,000円 | 57,600円 | ||
| 年間上限 144,000円 (※3) | 多数回該当の場合は44,400円 (※2) | ||||
| 住民税 非課税世帯 |
低所得II(※4) | 8,000円 | 24,600円 | ||
| 低所得I (※5) | 15,000円 | ||||
※1 … 「現役並み所得者」とは、同一世帯内に市民税課税所得145万円以上である70歳以上の国保被保険者がいる場合に適用される自己負担限度額の区分であり、一部負担金の割合も3割になります。
ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が二人以上(国保から後期高齢者医療制度に移行した人も含む)で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により「一般」区分と同様になります。
加えて、昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、世帯の70歳以上の被保険者に係る旧ただし書所得(総所得金額等-基礎控除)の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様になります。
※2 … 多数回該当の場合の限度額は、過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回目以上のときに適用します。
※3 … 年間上限とは、8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担限度額です。
※4 … 「低所得II」とは、世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税の世帯である場合に適用される所得区分です。
※5 … 「低所得I」とは、世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税且つ、各々の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯である場合に適用される所得区分です。
75歳になり、国保から後期高齢者医療制度に加入した場合、その月に限り国保と後期高齢者医療制度のそれぞれの自己負担限度額が半額になります。
ただし、各月1日生まれの人は除きます。
自己負担額の計算にあたって注意すること
- 月の1日から末日(暦月ごと)の受診分について計算します。
- 複数の医療機関にかかった場合、医療機関ごとに分けて計算します。また、同じ医療機関でも、入院・外来・歯科は分けて計算します。
- 調剤薬局分は、処方もとの医療機関に含めて計算します。
- 70歳以上75歳未満の人は、医療機関・歯科・調剤薬局の区別なく合算して計算します。
- 入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは支給の対象になりません。
- 多数回該当の制度がある適用区分の場合、過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
- 国保の県単位化により、平成30年8月以降は、三原市へ転入または三原市から転出した場合でも、同一都道府県内での転居であり、且つ転居前と同一の世帯であると認められるときには、多数回該当の回数が通算されます。
- 三原市へ転入または三原市から転出した月の自己負担限度額は、転入出前後の市区町村でそれぞれ本来の自己負担限度額の2分の1として適用されます。
同じ世帯で合算して計算できる場合
一つの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上(複数医療機関 ・ 複数人など)支払った場合、それらを合算した金額が、自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた分が支給されます。
▼合算して計算できる例
- 一人で複数の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上を支払った場合
- 同じ世帯の人が、それぞれ医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上を支払った場合
なお、70歳以上75歳未満の人は、自己負担の金額にかかわらず、合算して計算します。
「自己負担限度額」の適用を受けるには
入院するときや高額な外来診療を受けるとき、医療機関等の窓口での負担を限度額までとするには、次のいずれかの方法で限度額適用区分を確認してもらう必要があります。
(1) マイナ保険証で受診
(2) 資格確認書で受診し、医療機関がオンライン資格確認で限度額適用区分を照会することに同意する
(3) 資格確認書で受診し、申請により交付された「※1限度額適用認定証」または「※2限度額適用・標準負担額
減額認定証」を提示する
※1 住民税課税世帯に交付
※2 住民税非課税世帯に交付
ただし、次の方は医療機関等に限度額適用認定証等を提示する必要があります。
●オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合
●住民税非課税世帯の方で、直近1年間の入院日数が90日を超え、食事療養費が減額の対象になる場合
|
【限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの】
※郵送での申請も受け付けています。 [郵送での申請に必要なもの]
(申請書ダウンロード) ・国民健康保険限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定申請書 [PDFファイル/67KB] ・国民健康保険限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(記入例) [PDFファイル/179KB]
[郵送の場合の注意事項]
|
厚生労働大臣が指定する特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病で、高額な治療を長期間続ける必要がある場合、医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提示すれば、同一医療機関に支払う自己負担金は月額10,000円(※)までとなります。
特定疾病療養受療証が必要な方は、保険医療課または各支所地域振興課の窓口で申請してください。
(※)人工透析が必要な慢性腎不全の治療を受けている方で、70歳未満の上位所得者は,
自己負担月額は20,000円までとなります。
対象となる疾病(厚生労働大臣の指定する特定疾病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症
|
【特定疾病療養受療証の申請に必要なもの】
(申請用紙ダウンロード) |