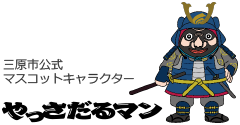本文
市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入する取り組みについて
本市では、土砂災害の危険性が高い土地への住宅等の建築を抑制するため、「市街化区域」の中に指定された“土砂災害特別警戒区域”の範囲について、段階的に都市計画の区分を「市街化区域」から「市街化調整区域」へ見直す「逆線引き※」の取り組みを進めていきます。
|
※「逆線引き」とは |
取り組みのポイント
・「市街化区域」内に指定されている“土砂災害特別警戒区域”は、本市には350か所程度あります。
・このうち「市街化区域」の縁辺部で、現在建物が建っていない場所(40か所程度)を先行して、令和4年度から令和6年度までの3か年度で「市街化調整区域」に見直していきます。
(取り組みのイメージ)

出典:広島県HP
先行的に実施する箇所の取り組み内容
○令和4年度の取り組み内容
・現地調査や土地所有者への説明会等を行い、都市計画(区域区分)変更の素案を三原市が作成
○令和5・6年度の取り組み内容
・令和4年度に作成した素案をもとに、広島県において、縦覧・公聴会、都市計画審議会等の都市計画の手続きを実施
(参考)広島県の取り組み
【目的】
「市街化区域」内の災害リスクの高い地域を対象に、「市街化調整区域」への見直しを行うことで、安全な地域への居住の誘導を図る。
【位置づけ】
広島県の総合計画である「安心・誇り・挑戦 ひろしまビジョン」に“災害に強い都市構造の形成”を位置づけ、令和3年3月策定の「広島県都市計画区域マスタープラン」において、『逆線引き』の取り組みを推進することとしている。
【目指す姿】
| 現在 | 概ね20年後 | 50年後 | ||
| 市街化を促進する 「市街化区域」内において、災害リスクの高い “土砂災害特別警戒区域”が多く含まれており、土地利用規制が十分に機能していない。 | → | 「市街化区域」内の “土砂災害特別計画区域” において、『逆線引き』が概ね完了し、災害リスクの高い区域において新規居住者がほぼいない。 | → | 災害リスクの高い区域において、土地利用規制(新築や建て替えなどの抑制)が十分に機能し、災害リスクの高い区域に居住する人が概ねいない。 |
【取り組みの進め方】
対応箇所が多数あることから、段階的に進めることとし、まずは市街地の広がりを防ぎ、低未利用地への居住や店舗等の新築を抑制する観点から、「市街化区域」の縁辺部で住宅・店舗・工場等の都市的土地利用が行われていない箇所(山林・田・畑などの土地)から先行的に実施する。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/105/gyakusenbiki.html
(※広島県ホームページへのリンク先です。参考にしてください。)
|
用語説明 |