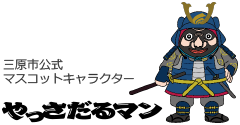本文
債権管理条例を制定しました
債権管理条例制定の目的
市が有する公債権及び私債権を対象とした統一的な処理基準を定め、債権管理の一層の適正化を図ることを目的としています。
滞納時の債権管理の手順を明確化し、公平性を高めます。
債務者への一定した対応を行い、行政サービスの向上を図ります。
なお、条例の施行は、平成30年4月1日です。
条例の概要
第1条関係(目的)
この条例は、市の債権の管理について統一的な処理基準を定め、債権管理の一層の適正化を図ることを目的としています。
第2条関係(定義)
市が所有しているすべての債権をこの条例の対象とし、市の債権、強制徴収公債権、非強制徴収公債権等について、それぞれ定義しました。
第3条関係(他の法令等との関係)
法令、他の条例又はこれらに基づく規則に定めがある場合を除いて、この条例の規定に基づいて事務処理を行うこととします。
第4条関係(市長等の責務)
市長等は、法令、条例又はこれらに基づく規則の定めるところにより、市の債権の適正な管理及び事務処理を行わなければならないこととします。
第5条関係(台帳の整備)
市の債権を適正に管理するために、規則で定める事項を記載した台帳を整備することとします。
第6条関係(督促)
履行期限までに履行されない場合は、期限を指定して督促しなければならないとします。
第7条関係(公債権に係る延滞金)
公債権に係る督促をした場合、履行期限までに履行されない場合、延滞金を徴収することとします。また、やむを得ない事情があると認める場合は、延滞金を免除することができるとしています。
第8条関係(私債権に係る遅延損害金)
私債権に係る督促をした場合、履行期限までに履行されない場合、遅延損害金を徴収することとします。
第9条関係(相殺)
履行遅滞の債務者に対して市が債務を有するときは、その履行遅滞となっている市の債権を市が有する債務と相殺することができるとしています。
第10条関係(滞納処分等)
強制徴収公債権について、法令や条例の規定にもとづいて、滞納処分や処分の緩和措置を行うこととします。
第11条関係(強制執行等)
非強制徴収債権について、督促をしてもなお履行されない場合には、強制執行の措置をとることとします。
第12条関係(履行期限の繰上げ)
市の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知を行わなければならないこととします。
第13条関係(債権の申出等)
市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合には、配当の要求等、債権の保全のための手続きをとらなければならないこととします。
第14条関係(徴収停止)
非強制徴収債権について、債務を履行させることが著しく困難な場合や不適当であると認めるときは、徴収を停止できることとします。
第15条関係(履行延期の特約等)
非強制徴収債権の債務者が、資力がないなどの理由で期限までに履行できない場合は、履行期限を延長又は適宜分割して履行期限を定めることができることとします。
第16条関係(免除)
非強制徴収債権の債務者が、当初の履行期限から10年を経過してもなお資力が回復しない場合は、債務を免除できることとします。
第17条関係(債権の放棄)
非強制徴収債権について、履行できない一定の条件を満たした場合には、債権の放棄ができることとします。
第18条関係(報告)
非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならないとします。
第19条関係(委任)
この条例に定めるもののほか、必要な事項については、債権管理条例施行規則等で別に定めることとします。